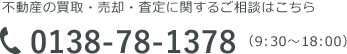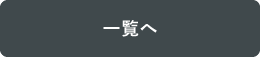日本酒の「冷や」を楽しんでみませんか?
2024/05/19
―ワインエキスパートがそっとお伝えする、常温の奥深さ―
日本酒には、温度によって実にいろいろな呼び名がありますよね。
「雪冷え」「花冷え」…そして今回のブログ記事の主役、“冷や”。
実はこの「冷や」、
日本酒の魅力がいちばん素直に現れる温度帯なんです。
ワインの世界でも温度はとても大事で、
冷たすぎれば香りが閉じてしまいますし、
温かすぎるとアルコールが前へ出てきます。
日本酒も同じで、常温に近い「冷や」は、
酒がいちばん自然体でいられる温度なんですよ。
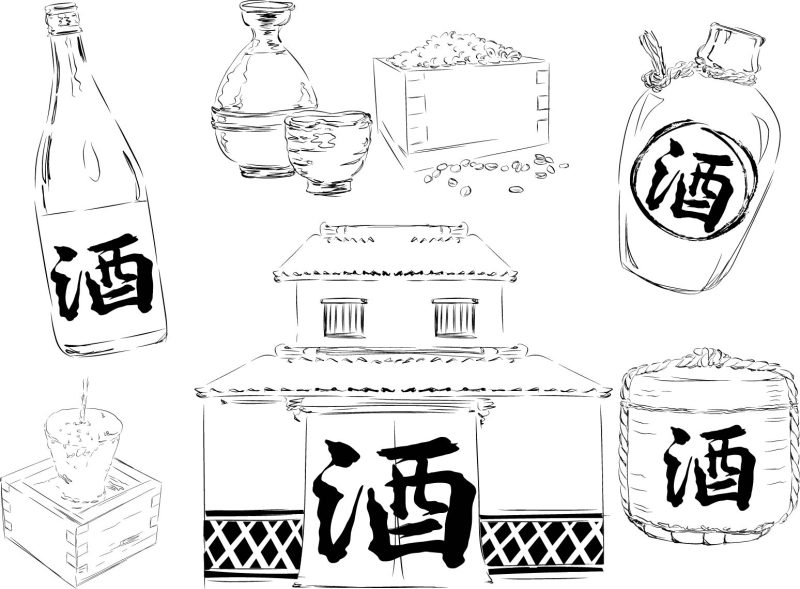
「冷や」だと、日本酒の“素顔”が見えてきます
冷蔵庫から出したての冷酒はキリッとして気持ち良いですよね。
でも、その爽やかさの裏で、
実は香りや旨味がまだ眠っていることがあります。
ところが「冷や」(だいたい15〜20℃)になると、
ふわりと自然に香りが立ち上がり、
米の甘みや酸味がバランスよく広がり、
酒そのものの個性が、まるで顔を出すように感じ取れる
まさに“等身大の日本酒に会える”温度なんです。
ワインで言うなら、品種のキャラクターやテロワールが
一番掴みやすい温度帯、というニュアンスに近いですね。
実は「アル添酒」も、冷やだと格段に良くなるんです。
「醸造アルコール添加(アル添)」って聞くと、
ネガティブなイメージを持つ方もいますよね。
でも、ちょっとだけ誤解されている技術なんです。
冷やの温度だと、アル添酒ってすごく綺麗にまとまるんですよ。
たとえば…
香りが雑味なくスッと整う
後味がきれいに切れて、余韻が長すぎない
吟醸香も“ちょうどよく”引き立つ
低温だと軽さばかりが目立ってしまうこともありますが、
冷やなら、蔵が意図してつくったバランスの良さが見えてきます。
ワインでも補酸やアルコール調整は普通に行われていますから、
日本酒のアル添も「技術としての美しさ」と捉えると、
見え方が変わってくるんです。
もし冷やで飲むなら、このタイプを試してみてください
専門的な話を少し噛み砕いてお伝えすると、
「冷や」で魅力がぐっと深まるのはこんなお酒です。
純米酒(特に生酛・山廃のしっかりタイプ)
控えめな香りの純米吟醸
本醸造や特別本醸造のうまみ系
少しだけ熟成した日本酒(1〜2年ほど)
冷蔵庫で冷たくして飲む時とは表情がまるで違うことがあります。
「え?これ同じ酒?」と驚かれる方も多いんです。
「冷や」は日本酒の“真価”に近づく温度です
香り華やかな吟醸酒を冷酒で飲むスタイルが広まっていますが、
酒そのものを理解したいなら、冷やは外せません。
造り手の考え、米の力、酒の設計──
そういった“見えない部分”に触れられるのが、冷やの魅力なんです。
もし次に日本酒を手に取ることがあったら、
ぜひ一杯だけでも「冷や」で味わってみてください。
きっと、新しい日本酒の扉が開きますよ。